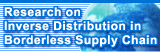エコデザイン 2006 アジア・パシフィックシンポジウム
エコデザインを世界へ
5.開催の趣旨
エコデザイン学会連合では、1999年以来、国内4回、国際4回と開催して来たシンポジウムを今年はアジア・パシフィックシンポジウムとして開催します。ここでは、今までに築いてきた実績を踏まえつつ、我が国発の環境技術を世界に広めかつ実践する為の基盤を強固にする事を目指します。何卒、この趣旨にご理解を賜り、多くの研究者、技術者、教育者、産業人、行政人の参加をお願いする次第です。 |
6.募集要領 (締め切りました)
日本語の発表の場合
アブストラクト(文字数 400 字程度)に、(1)題名(英文併記)、(2)著者(英文併記)、(3)所属学会名(英文併記)、(4)所属機関名・所在地(英文併記)、(5)連絡先氏名・住所(英文併記)・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス、(6)下記、講演カテゴリー番号(1〜12)、(7)キーワード(英文併記)を明記し、原則E-Mailにより、ご投稿下さい。(郵送の場合、A4版の用紙を用い、「エコデザイン 2006APシンポジウム投稿申込み」と添え書きした封筒に入れる。)
|
英語の発表の場合
英文のアブストラクト(200語程度)に、上記(1)〜(7)を明記し、上記により申し込んで下さい。 |
参考
この案内では、試みとして「何に役立てる発表か」が直感的に理解できるカテゴリー分けを採用してあります。また、参考に挙げたキーワードも一見無秩序に配列しました。これは、学問体系による発想の縛りを解くためとご理解下さい。最終のプログラムでは、投稿された講演の集まりから新たなカテゴリーを編成します。 |
7.講演カテゴリー
既存の技術に比較し、1.物質消費、エネルギー消費を大きく節減できる。2.環境に蓄積する毒性物質を使わない。人に対する毒性を有する物質を使わない。3.再処理の手段のない材料は使わないなどの特性を有する製品を作り出す技術、4.製品保有からサービスへの展開を支える技術。5.未使用エネルギーを、変換、抽出、活用する技術、6.加工に適さない材料を使える材料にする技術。7.社会システムを変革する事で、材料、エネルギーを使わないようにする考え。8.環境に廃棄される有害物質を追跡する技術。再処理する技術。9.リサイクル、リユース技術、10.以上の特性のいずれかを実現した製品、あるいは、実現するための工程、システムの提案。実施例。11.以上に関係した方法論、教育法、研究方法の提案。12.その他、新しい環境調和の考え方、方法論、ライフスタイルの提案。
|
8.発表形式
原則的には口頭発表(1件質疑応答5分を含み20分を予定)とします。また、発表内容や件数等によりポスター発表を行って頂く場合があります。プログラム編成は9月に発行予定のプログラムに掲載します。 |
9.キーワード(参考)
論文の内容に適合するキーワードを抜粋して下記に示します。
DfE、DfX(デザイン for X)、ライフサイクル設計、エコマテリアル、グリーンケミストリー、モジュラー設計、サービスエンジニアリング、QFD、TRIZ、TOPSIS、MSDA、同時/協調設計エンジニアリング、資源節減、エネルギー節減、エネルギー回収、リユース、リサイクリング技術、廃棄物処理技術、リサイクリングの自動化技術、情報技術、鉛フリー半田、環境教育、エコラベル、環境会計、情報共有、環境報告書、環境マネージメントシステム、環境レーティング、製品ライフサイクルマネージメント、エコデザインのための評価方法、環境性能指標、環境効率、ファクターX、持続性評価のためのグレーディングまたは指標、LCA、ライフサイクルコスト、ITアプリケーションの環境負荷評価、ITの社会影響、LCD、ライフサイクルシミュレーション、生活密着型環境対応、環境対応実装技術、エコ製品、インバースマニュファクチャリング、迅速循環、生産/廃棄プロセスの環境評価、リバウンド効果、分離技術、接合技術、鉛フリー接合、銅・銅直接接合、金・錫接合、MEMS、色素増感、燃料電池、水素エネルギー、サステナブル・ハウジング、ハイブリッドエンジン、ITS、バイオマス、電子出版、グローバルリサイクリング、環境調和技術ロードマップ、新技術活用(GPS、RFID、電子ペーパー、インクジェット)、CO2排出権取引、地球温暖化防止、京都議定書、ESCO事業、ナノ構造シリコン、ナノ材料、SPR計測、環境計測技術、サステナブル社会、エコタウン、グリーン調達、逆配送システム、環境汚染防止、廃棄物処理、エコビジネスモデル、バリューチェイン/サプライチェーンマネージメント、省物質のためのサービス戦略、廃棄物及び廃水処理ビジネス、消費性向分析、消費者行動モデル、エコファンド、ゼロエミッション、リースシステム、環境調和型製品、モジュラー製品、長寿命製品、資源節減型及びエネルギー節減型製品、アプグレード可能製品、製品(もの)からサービスへの展開、環境調和製造プロセス、保全技術、出荷後サービス、集荷プロセス、分解プロセス
以上 |
10.問い合わせ窓口
11.日本語発表の方の送り先E-Mailアドレスとアブストラクト投稿シート (締め切りました)
| 1) |
題目・英文題名 |
| 2) |
投稿者指名・英文氏名 |
| 3) |
所属名・英文所属名 |
| 4) |
連絡先住所、電話、Fax、E-Mail・英文連絡先住所 |
| 5) |
講演カテゴリー番号(下記から選択して下さい)
| 1. |
物質消費、エネルギー消費を大きく節減できる製品あるいは製法 |
| 2. |
環境に蓄積する毒性物質、人に対する毒性を有する物質を使わない。製品あるいは製法 |
| 3. |
再処理の手段のない材料は使わない製品およびそれを作り出す技術 |
| 4. |
製品保有からサービスへの展開を支える技術 |
| 5. |
未使用エネルギーを、変換、抽出、活用する技術 |
| 6. |
材料の革新技術 |
| 7. |
持続的発展に向けた社会システムの変革 |
| 8. |
環境に廃棄される有害物質を追跡する技術。再処理する技術 |
| 9. |
リサイクル、リユース技術 |
| 10. |
以上のいずれかを実現した製品、工程、システムの提案、実施例 |
| 11. |
以上に関係した方法論、教育法、研究方法の提案 |
| 12. |
その他、新しい環境調和の考え方、方法論、ライフスタイルの提案 |
|
| 6) |
日本語キーワード
英語キーワード |
| 7) |
日本語アブストラクト(約400字)
英語アブストラクト (約200 Words) |
12.様式のダウンロード(アブストラクト採択後の論文用Template)
全ての論文は、 Instruction と Format で示される様式に従って書いてください。
日本語で書く場合は、 Format が Instruction を兼ねています。ここからダウンロードできます。
作成要項 |
 |
 |
|
|
以上 |